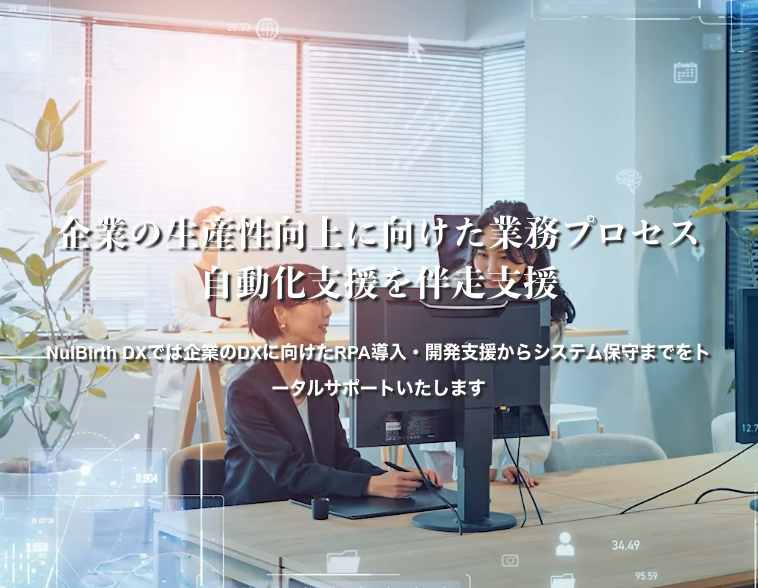DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、Digital Transformationの略語となります。近年では、一般的にビジネス用語で使われることが多くなり、聞いたことはあるけれども、具体的に何を示すのか気になる方も多いのではないでしょうか。
Digital「デジタル」Transformation「変容」という意味で、DXを直訳すると「デジタルによる変容」となります。デジタル技術を活用することにより、生活やビジネスが変容していくことを一般的にDX呼びます。
DXは「単にIT化することではないのか」「AIやIoTを導入することではないのか」「紙業務などのアナログ業務をデジタルに置き換えることではないか」と理解している方もいるのではないでしょうか。
ここ数年は、企業の経営者たちが集うビジネスカンファレンスでも「DX」について語られるケースは増える一方、実行施策の一例を聞くと、過去と変わらない「既存の業務システムのリプレイス導入(載せ替え)」であったことも見受けられます。DXという抽象的な解釈が当てはまるキーワードによる、ある種の弊害なのかもしれません。
DXとIT活用、あるいはIT化とは、大きく意味合いが異なります。この違いを理解していないと、DX推進の方向性がずれてしまう可能性があります。今回は、DXの定義・概要についてご説明するとともに、DXとIT活用の違いについて解説します。
DXの定義とは?
先述のとおりDXとは、Digital Transformationの略語です。Transformationは「変容」という意味なので、DXを直訳すると「デジタルによる変容」となります。デジタル技術を用いることで、生活やビジネスが変容していくことをDXと言います。
DXに関する厳密な定義があるわけではありませんが、経済産業省では、「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」において、以下のようにDXを解釈しています。
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」
このように、DXはビジネス用語として定着しつつあります。データやデジタル技術によって、製品やサービス、ビジネスモデルを「変革」してこそDXと言える点がポイントです。
DXとデジタイゼーションとデジタライゼーションとの違い
DXと似た用語として、デジタイゼーション(Digitization)やデジタライゼーション(Digitalization)も存在します。非常に混同しやすいのですが、経済産業省の取りまとめた「DXレポート2」に記載されている以下の図を頭に入れておくと理解しやすいのではないでしょうか。
このように、DXが全社規模で価値創出にこだわるデジタル化であるのに対し、デジタライゼーションは特定のプロセスに限ったデジタル化、デジタイゼーションは紙やパンチカードなどの物質的な情報をデジタル形式へ変換することを指します。
自社の目指す変革の方向性が3つのうちどれに当たるのか、そして実際に進めている施策内容はどれに当たるのかを随時すり合わせるようにするとよいでしょう。
欧米におけるDXの定義と変遷
DXという言葉は、2004年にスウェーデンのウメオ大学に所属するエリック・ストルターマン教授が提唱したとされています。テクノロジーの発達が人々の生活を改善することを指し、研究者は、その変化を正しく分析・議論できるようアプローチの方法を編み出す必要があると主張しました。
この点からも明らかな通り、DXは学問的な用語として提唱されました。しかし、ビジネスの世界にさまざまなデジタル機器やソーシャルメディアなどが入り込んでいくにつれて、2010年代を通して、少しずつDXはビジネス用語として浸透していったと考えられます。
Transformationの言葉が示す通り、デジタル技術が発達することでビジネスや生活を劇的に変容させる、というのが広く受け入れられたDXの考え方です。日本でも、こうしたDXの理解が広まっていきました。
CX・UX……類似キーワードとの違い
DXのように、「~X」という略語を持つビジネス用語が2つ存在します。まずCXとはCustomer Experienceの略語で、「顧客体験」の意味を持ちます。Webサイトやカスタマーサポート、営業マンなど、顧客が製品・サービスや企業に接する際の体験の価値を指しています。DXは、デジタル技術を駆使してCXを向上させる試みです。
UXはUser Experienceの略語で、「ユーザー(使用者)体験」の意味です。ユーザーが企業の製品・サービスに接する際の体験の価値を指します。CXと似ていますが、UXの方はどちらかと言うと製品・サービスそのものやWebサイトなどの使いやすさを指すのに対し、CXはより広くアフターケアなどを含めることが多いです。
IT化とDXの違いと関係性
では、IT化やIT導入とDXの違いをご説明します。DXの持つ意味が、IT化と比較することでより明確に理解できるでしょう。
IT化とDXの関係が手段と目的であること、またIT化が既存の業務プロセスの効率化を目指すのに対し、DXがもっと大局的なレベルで製品・サービスやビジネスモデルの変革を目指す点を説明していきます。
IT化の意味と事例
明確な定義があるわけではありませんが、一般的にIT化、IT導入というと既存の業務プロセスは維持したまま、その効率化・強化のためにデジタル技術やデータを活用するというイメージがあります。
例えば、電話や手紙であった連絡手段が、Eメールやチャットツールなどに置き換わったのはその典型です。連絡の是非自体は問われることなく、ツールを導入することで効率化が図られたことになります。近年ではRPAやAI、ビッグデータなど大きな可能性を秘めた技術が次々と登場していますが、既存プロセスの効率化=IT活用に留まるケースが少なくありません。
IT化とDXの関係は「手段と目的」
前述の通り、DXはデジタル技術の活用によって製品・サービスやビジネスモデルに変革をおこすものです。したがって、IT化はDXの手段であり、DXはIT化の先にある目的であると考えられます。
もちろん、IT化の目的が必ずDXである必要はなく、既存プロセスの効率化だけが目的であっても全く問題はありません。しかしながら、なぜITを活用したいのかが明確でないと、単に新しい技術を使ってみることだけが目的となってしまい、利益を生まないIT活用になる可能性もあります。
IT化による変化とDXによる変化の違いとは?
IT化による変化は「量的変化」、DXによる変化は「質的変化」と言えます。
IT化は、既存プロセスの生産性を向上させるものです。何がどのように変化するか、社内でも分かりやすいのが特徴です。それに対してDXは、プロセス自体を変化させます。単に「作業時間が減る」「●●の作成プロセスを自動化する」などの分かりやすい変化ではなく、「顧客との接客方法がデジタルを通じて根本的に運用が変わる」「物流の配送計画をデジタルを用いて確認プロセスが抜本的に変わる」など、会社全体に関わるようなドラスティックな変化であるのが特徴です。
DXがビジネスに求められる理由と日本企業の課題
DX=デジタルによるビジネスの変革がなぜ必要になるのでしょうか。ここでは、DXの意義と日本企業ならではの課題について考えていきます。
テクノロジー「だけ」では優位性につながらない
DXの意義は、デジタルの力によってビジネスモデルなり、製品・サービスなりを変革することで、市場における優位性を打ち立てることにあります。ここで問題になるのが、単にテクノロジーを入れるだけでは優位性につながらないことです。
パソコンやスマートフォンのようなデジタル機器はもちろんのこと、AIやIoTのような高度なテクノロジーでさえ、近い将来にはあって当たり前になっていきます。いくらAIが大量のデータを迅速に処理してくれたとしても、AI自体は革新的なアイデアを持っているわけではありません。
つまり、テクノロジーやそれを使えるスタッフがいるだけで、すべてがうまくいくわけではなく、経営層が全社的な経営課題としてテクノロジーによるビジネスモデルの変革を考えることが必要不可欠です。
既存システムの老朽化とIT人材の活用
経済産業省によると、日本企業でもDXの必要性を認識し、DXを推進する取り組みが進められているものの、成功には至っていないケースが多いようです。
日本企業のDXを阻む問題として、既存システムの老朽化と人材不足の2点が挙げられています。 調査では、約8割の企業が老朽化したシステムを抱えており、約7割の企業がそれをDXの足かせと感じているという結果が出ています。
この点は、人材不足という問題とも関わっています。IPAによればDXを進める人材が大幅に不足していますが、その要因のひとつとして老朽化したシステムの運用・保守に人材を割かれてしまう点を挙げることができるためです。仮に先端的な技術を学んだIT人材が入ってきても、老朽化したシステムの運用・保守に充てざるを得ず、結果として高い能力を使いこなせていなかったり、離職してしまったりと、IT人材の確保に苦労している実情が読みとれます。
以上の課題を踏まえると、日本企業がDXを進めるためには、既存システムを含めたシステムの再構築と、IT人材の育成・活用が大きな鍵となることがわかります。